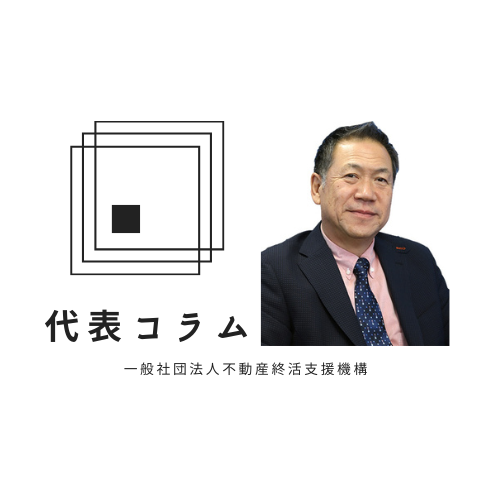空き家問題
2024年度、日本全体で空き家といわれているものは約900万戸となりました。
このうち賃貸用としての空き家が約443万戸、別荘などセカンドハウスとしているのが約38万戸、そして問題視されている空き家が約385万戸あるとのことです。
一方で、2024年に新築されている住宅は約79万戸ありました。このままの推移で進むと2043年には4軒に1軒は空き家になっているという予測があるようです。私の住む岩手県においてはもっと高い割合で空き家が増えることも考えられます。この増加する空き家を、どこかで食い止める必要があるわけです。
さて、空き家問題は、それぞれの家族・家庭によって、さまざまな事情で発生し、年々増加しています。
活用や売買取引が難しい、需要のない地域と、需要の多い地域では状況は大きく異なっています。需要のない地域、つまり田舎といわれる所は、個人だけではどうすることもできないという現実があります。若者は流出し、産業も衰退してしまい、なかなかこれという施策はできないのが実情です。行政も尻込みをしている、というところもあるように聞こえてきます。できればこうした地域の不動産所有者は空き家のまま放置せず、建物を解体して更地の状態にしてほしいものです。老朽化した建物はさまざまな問題を引き起こします。

空き家にしたまま放置しておくと、見栄えはよくなく、不気味な建物として存在することになります。又、犯罪に使われる可能性もあり、地域の住民にとっても大変に迷惑な問題となります。せめて更地であればこのような不安もなくなるものだと考えられますが、解体費の捻出ができないとか、更地のままだと固定資産税の軽減措置が受けられない等といった現実もあり、簡単には進みません。補助金等が出る地域もありますので、活用を検討したり、市町村に相談することも必要です。いずれにせよ、所有者は“不動産所有者としての責任と自覚”を持ってほしいものだと思います。
一方、活用や取引の需要の多い地域は、所有者本人の意思次第で如何様にも使うことができます。しかしそれすら行わず、そのまま放置していることが多くの問題を引き起こしています。こうしたケースもまた、様々な事情があるようです。例えば、相続問題のこじれや、その家に対しての愛着(思い出)、また所有者としての責任の薄さなどが挙げられます。自分本位の無責任な考えで空き家のままにしておくことは、隣接地だけでなく地域社会に多大な迷惑をかけているのです。
相続のこじれにより手がつけられないというケースもあります。例えば、不動産の所有者となる相続人が、一人ではなく複数人いるケースです。それぞれが持つ思惑や、欲得、私情などが複雑化して、意志判断ができなく、放置されてしまっている場合もかなりあるのが現状のようです。
登記未了不動産
 近年、所有者不明の不動産も増えてきています。正確に言うと、何代にも渡って相続登記がされておらず、所有者が特定できない不動産のことです。通常、相続が発生すると不動産は相続人に相続されます。しかし、この時に相続登記をしないままにしてしまうということが、今までたくさん起きていました。それが何代も続くと、相続の権利者がどんどん増えてしまい、次第に全員での話し合いが困難になり、解決不能になっていくのです。
近年、所有者不明の不動産も増えてきています。正確に言うと、何代にも渡って相続登記がされておらず、所有者が特定できない不動産のことです。通常、相続が発生すると不動産は相続人に相続されます。しかし、この時に相続登記をしないままにしてしまうということが、今までたくさん起きていました。それが何代も続くと、相続の権利者がどんどん増えてしまい、次第に全員での話し合いが困難になり、解決不能になっていくのです。
それだけでなく、既に弁済がされている債務の抵当権が抹消されていなかったり、その他の権利も抹消されていないといった事も多々あります。
このように不動産所有者の特定が困難になった結果、隣接する土地との境界が確定できず、売却することができないといったことが起きています。他にも、所有者不明地を含めた一帯の地域で計画されている宅地開発や公共事業の場合も、所有者が不明なため、承諾をもらえず買収ができず計画が進まないということが起きます。こうした事態は、地域としての計画が成り立たず、大変な問題になっています。
他にも、農地や山林などを相続して、登記せず放置しているものも多々あるようです。自分にとって、不必要な土地は興味がないと言った所でしょうか。特に山林などは、境界がはっきりせず、場所自体を特定できないこともあるようです。
ちなみに、今、日本全体で所有者不明は、九州全体ぐらいの面積があるようです。これらもどこかで歯止めをかけないと大きなつけを残すことになります。2024年には新たなルールとして、相続登記の義務化が求められるようになりました。今後こうした取り組みによって少しでも改善されていくことを祈るばかりです。
未管理不動産
近年、各地で台風や大雨などによって土砂崩れなどの自然災害が発生し、甚大な被害を起こしています。以前土砂崩れが起きた現場がテレビなどに映し出された際に、斜面に残った木々がとても細く、密集していたのが印象的でした。
この様な災害はどうして起きたのでしょうか。不動産管理という一面から考察してみます。
昭和20年代から30年代にかけて、山林に人工林として杉やヒノキなどを植林が盛んに行われるようになりました。広葉樹の木を伐採し、針葉樹を植林するものです。
伐採した広葉樹は薪炭などの燃料として、植林された杉やヒノキは建築資材等としての目的で山林の開発がされていきました。この人工林は定期的な間伐や、下草刈りなどの管理が大変重要で、これらを怠れば様々な問題が起きてくるわけです。間伐をしない山林では、1本1本の木が細く上に伸びていき密集していきます。それによって太陽の光が地表に届かず下草や、低木の木が生えなくなって土の状態のままになります。こうした土は、根が張られていないため、表度が柔らかい状態のままとなり、災害が起きやすい山林ができてしまいます。
例えば、大雨が降った時には、その雨が土石となって一気に川に流れてしまいます。また、土に浸透して地盤を緩めることで、土砂崩れとなり甚大な災害が引き起こされています。
近年、薪炭などの燃料や建築資材の需要が少なくなったことで、山林の整備をしない人が増え、放置され管理されていない山が増えて来ました。これらが、災害が頻繁に起きる原因の一つとも言われています。

最近では、企業やボランティア団体が山林の整備をしていますが、所有者不明のため承諾が取れず整備ができないということがおきているそうです。「所有者不明不動産」「未管理不動産」が増えることで、社会全体に対し多大な影響と、大変な損害を与えています。これらは、空き家問題と同じく深刻であり、現時点では解決不能の状態でありますが、世間からは関心が薄く、さほど話題にも上がらないように感じます。所有者自身が不動産に対し無知なことや、偏った考え、無責任によることで起きているのではないでしょうか。
「空き家問題」「所有者不明不動産」「未管理不動産」の問題は大変深刻な問題です。せめて、所有者だけでも明確にしておかなければ、何をするにも問題解決ができなくなることになります。不動産を所有する者は、責任を持った「不動産の終活」を考えてもらいたいものです。